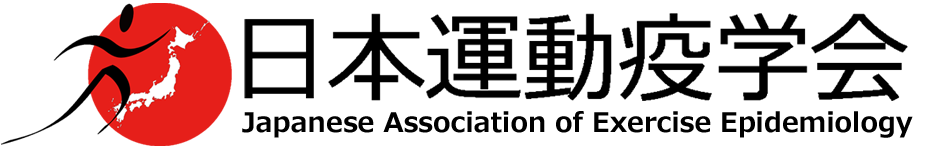学会概要
理事長あいさつ
2020 年 10 月に井上茂先生から理事長を引き継がせていただきました。特に今期は、副理事長を筑波大学の中田由夫先生、慶應義塾大学の小熊祐子先生のお二人にお願いし、盤石の体制を整えました。井上前理事長の方針を継承しつつ、更なる学会の発展に向けて尽力していきたいと考えております。2023 年 9 月までの任期となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。新たな体制として活動していくにあたり、本学会の課題や展望を整理し、以下について取り組んでいきたいと考えております。
■ 雑誌「運動疫学研究」の更なる充実
最近、運動疫学研究への投稿論文も増加しつつあります。査読の迅速化やJ-STAGE への掲載等に加え、特集・企画の試みなどが奏功しているためと思われます。さらに学会員の方々の良質な運動疫学研究の受け皿になるべく、編集体制を整えていきたいと思います。
■ 学会員の研究支援
コロナ禍の中、2020 年度は学術総会を延期、運動疫学セミナー等は中止せざるを得ない状況に追い込まれました。数年間は学会活動も様々な影響を受けることが予想されます。今後は、学術集会や運動疫学セミナー等を形式に拘ることなく充実させ、運動疫学に関する研究の歩みを止めることのないよう工夫していきたいと思います。
■ 社会への情報発信
コロナの真っ只中、2020 年 4 月には公式声明委員会が中心となって取りまとめた「新型コロナウイルス感染症流行下の身体活動不足・座りすぎ対策」が公開され、非常に多くのマスメディアに取り上げていただき、学会のプレゼンスを高めることができました。今後も、学会員へはもちろんのこと、社会に対しても学会としての考え方や学会員の研究成果等について積極的に情報発信を強化していきたいと思います。
■ 国際化の推進・国内他学会との連携
International Society for Physical Activity and Health には比較的多くの学会員の方が参加されており、学会としての目指すべき方向性も近いのではないかと思います。最近では、アジア・オセアニアの研究者を中心としたAsia-Pacific Society for Physical Activityが発足し、身体活動・座位行動に関する研究の推進体制が整えられつつあります。その他、国内の他学会も含め、積極的に学術交流することにより、本学会が最先端の運動疫学研究を生み出すプラットホームになれるように努力したいと思います。
未だコロナ禍で様々な制限も多く、学会活動も大変な状況ではございますが、会員の皆様の研究活動がこれまで以上に発展するよう努めていきたいと考えておりますので、皆様方には是非とも学会への積極的な関与をお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。


早稲田大学スポーツ科学学術院
岡 浩一朗
日本運動疫学会とは
現代社会において、技術革新に起因するライフスタイルの変化により、世界中の人々に身体活動の低下が蔓延しています。世界保健機関や厚生労働省、文部科学省をはじめ地域・職域、学術団体などがこの問題に取り組んでいますが、一筋縄では解決できない複雑な課題が残されています。
日本運動疫学会は、学術総会や運動疫学セミナー、分野横断型勉強会の開催、学会誌の発行、プロジェクト研究の募集、公式声明の公表、ニュースレターの発行など様々な活動を通じて、会員相互の交流の活性化や社会への情報発信を行い、学術の進展と国民の身体活動促進に資する活動を行っています。
日本運動疫学会設立趣意書
現代において、運動や身体活動の不足は主要な死亡原因である非感染性疾患(Non-communicable Diseases)の罹患や老化あるいはQOLの低下に関する重大な危険因子であることが、これまでの運動疫学研究によって明らかになってきました。今後はこれまでの運動疫学研究の成果を踏まえ、より多くの人々が運動や身体活動の不足を未然に防ぐとともに、今まで以上に運動や身体活動を促進することが求められます。
そのような状況を踏まえ、世界保健機関は「健康のための身体活動に関する国際勧告(Global Recommendations on Physical Activity for Health, 2010)」を発表し、非感染性疾患を予防するために必要な身体活動の頻度、継続時間、強度、種類、および総身体活動量などを詳細に示しています。そして、この勧告では身体活動の普及啓発や非感染性疾患の予防に関する世界的な働きかけの必要性を強く指摘しています。また、これに連動して、国際身体活動公衆衛生会議(International Congress on Physical Activity and Public Health, 2010)において「身体活動のトロント憲章」を採択し、運動や身体活動の不足を解消し、今まで以上に運動や身体活動を促進することを世界的規模で呼びかけています。
このような運動および身体活動と公衆衛生に関する国際状況を踏まえ、我が国では2013年から第4次国民健康づくり対策(健康日本21(第二次))がスタートするとともに、「健康づくりのための身体活動基準2013・身体活動指針(アクティブガイド)」が策定されました。これらの政策や指針の策定や改定が数多くの運動疫学研究の成果に基づいてなされていることから、今後運動疫学研究に対する期待がますます高まるものと考えられます。特に今後は、身体活動の不足や座位行動と健康障害に関する研究など、より幅の広い運動疫学研究が求められると考えられます。そして何よりも、それらの研究成果を疾病予防・健康の維持増進・老化予防といった現代の公衆衛生上の最大課題の解決につなげるためのポピュレーション・アプローチに関する研究や活動が極めて重要となります。
以上のような国内・外の運動疫学分野の状況を踏まえ、これまでの「運動疫学研究会」は以下の目的を達成するために発展的に解散し、新たに「日本運動疫学会」を設立します。その目的としては、第一に、我が国における運動および身体活動と健康に関連する研究をさらに発展させます。第二に、運動疫学研究者の育成環境および支援環境を充実させます。第三に、これらの研究成果を社会に還元するために、運動および身体活動の促進に対する包括的な国家政策の策定および行動計画の実施を積極的に支援します。第四に、日本体力医学会や日本公衆衛生学会などの関連学会との連携を密にして、健康関連分野のみならず、スポーツ・交通・都市計画分野などの行政機関、研究機関といった多くの関係者とのネットワークを構築し、国民の身体活動促進のための活動に寄与します。
2013年10月1日
利益相反
産学連携にかかる疫学研究活動において、社会的責任と高度な倫理性が要求されていることに鑑み、「日本運動疫学会 利益相反(COI)に関する指針」を策定いたします。本指針の目的は、本学会が会員などのCOI状態を適切にマネジメントすることにより、研究成果の発表やそれらの普及・啓発などの活動を中立性と公明性を維持した状態で適正に推進させ、本学会の社会的責務を果たすことにあります。本学会の各種事業に参加し業務を遂行したり発表したりする場合は、指針および細則の内容をご確認いただき、COI状態について開示のご対応をよろしくお願い申し上げます。
役員
各種委員会
役員
理事長
岡 浩一朗
早稲田大学
副理事長
小熊 祐子
慶應義塾大学
中田 由夫
筑波大学
理事
天笠 志保
帝京大学
安藤 大輔
山梨大学
石井 香織
早稲田大学
井上 茂
東京医科大学
岡田 真平
身体教育医学研究所
小野 玲
医薬基盤・健康・栄養研究所
甲斐 裕子
明治安田厚生事業団
鎌田 真光
東京大学
川上 諒子
明治安田厚生事業団
丸藤 祐子
駿河台大学
菊池 宏幸
東京医科大学
齋藤 義信
日本体育大学
笹井 浩行
東京都健康長寿医療センター研究所
柴田 愛
筑波大学
武田 典子
工学院大学
田島 敬之
東京都立大学
難波 秀行
大阪大学
原田 和弘
神戸大学
本田 貴紀
放射線影響研究所
門間 陽樹
医薬基盤・健康・栄養研究所
山北 満哉
山梨県立大学
監事
久保田 晃生
東海大学
重松 良祐
中京大学
顧問
顧問
種田 行男
中京大学
北畠 義典
埼玉県立大学
澤田 亨
早稲田大学
田中 茂穂
女子栄養大学
名誉会員
名誉会員
荒尾 孝
明治安田厚生事業団
川久保 清
共立女子大学
佐々木 英夫
広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター
下光 輝一
健康・体力づくり事業財団
編集委員会
委員長
笹井浩行
東京都健康長寿医療センター研究所
副委員長
中田 由夫
筑波大学
副委員長
門間 陽樹
医薬基盤・健康・栄養研究所
委員
江尻 愛美
東京都健康長寿医療センター研究所
金居 督之
金沢大学
川上 諒子
明治安田厚生事業団
清原 康介
大妻女子大学
柴田 愛
筑波大学
辻 大士
筑波大学
山北 満哉
山梨県立大学
学術委員会
委員長
本田 貴紀
放射線影響研究所
副委員長
辻 大士
筑波大学
委員
江尻 愛美
東京都健康長寿医療センター研究所
金居 督之
金沢大学
喜屋武 享
琉球大学
桑原 恵介
横浜市立大学
香村 恵介
名城大学
清野 諭
山形大学
田島 敬之
東京都立大学
原田 和弘
神戸大学
水島 諒子
国立保健医療科学院
門間 陽樹
医薬基盤・健康・栄養研究所
セミナー委員会
委員長
門間 陽樹
医薬基盤・健康・栄養研究所
副委員長
田島 敬之
東京都立大学
委員
天笠 志保
帝京大学
井上 茂
東京医科大学
鎌田 真光
東京大学
菊池 宏幸
東京医科大学
清原 康介
大妻女子大学
笹井 浩行
東京都健康長寿医療センター研究所
染谷 由希
順天堂大学
田島 敬之
東京都立大学
辻本 健彦
島根大学
山本 直史
愛媛大学
総務委員会
委員長
川上 諒子
明治安田厚生事業団
副委員長
丸藤 祐子
駿河台大学
副委員長
石井 香織
早稲田大学
委員
中潟 崇
医薬基盤・健康・栄養研究所
橋本 有子
お茶の水女子大学
松下 宗洋
東海大学
村上 晴香
立命館大学
渡邊 夏海
東京YMCA社会体育・保育専門学校
公式声明委員会
委員長
原田 和弘
神戸大学
副委員長
丸藤 祐子
駿河台大学
委員
阿部 巧
明治大学
上村 一貴
大阪公立大学
佐藤 真治
帝京大学
長阪 裕子
筑波大学
町田 征己
東京医科大学
宮脇 梨奈
明治大学
プロジェクト研究委員会
委員長
齋藤 義信
日本体育大学
副委員長
松下 宗洋
東海大学
副委員長
武田 典子
工学院大学
委員
小熊 祐子
慶応義塾大学
北湯口 純
身体教育医学研究所うんなん
城所 哲宏
日本体育大学
中村 学
慶應義塾大学
広報委員会
委員長
難波 秀行
大阪大学
副委員長
天笠 志保
帝京大学
委員
石毛 里美
介護老人保健施設青葉の丘
金森 悟
帝京大学
香村 恵介
名城大学
武田 典子
工学院大学
長阪 裕子
筑波大学
根本 裕太
神奈川県立大学
本田 貴紀
放射線影響研究所
渉外委員会
委員長
井上 茂
東京医科大学
副委員長
喜屋武 享
琉球大学
委員
阿部 巧
明治大学
大須賀 洋祐
国立長寿医療研究センター
小熊 祐子
慶應義塾大学
柴田 愛
筑波大学
杉山 岳巳
Swinburne University of Technology
事務局
事務局
佐野 芙美
早稲田大学